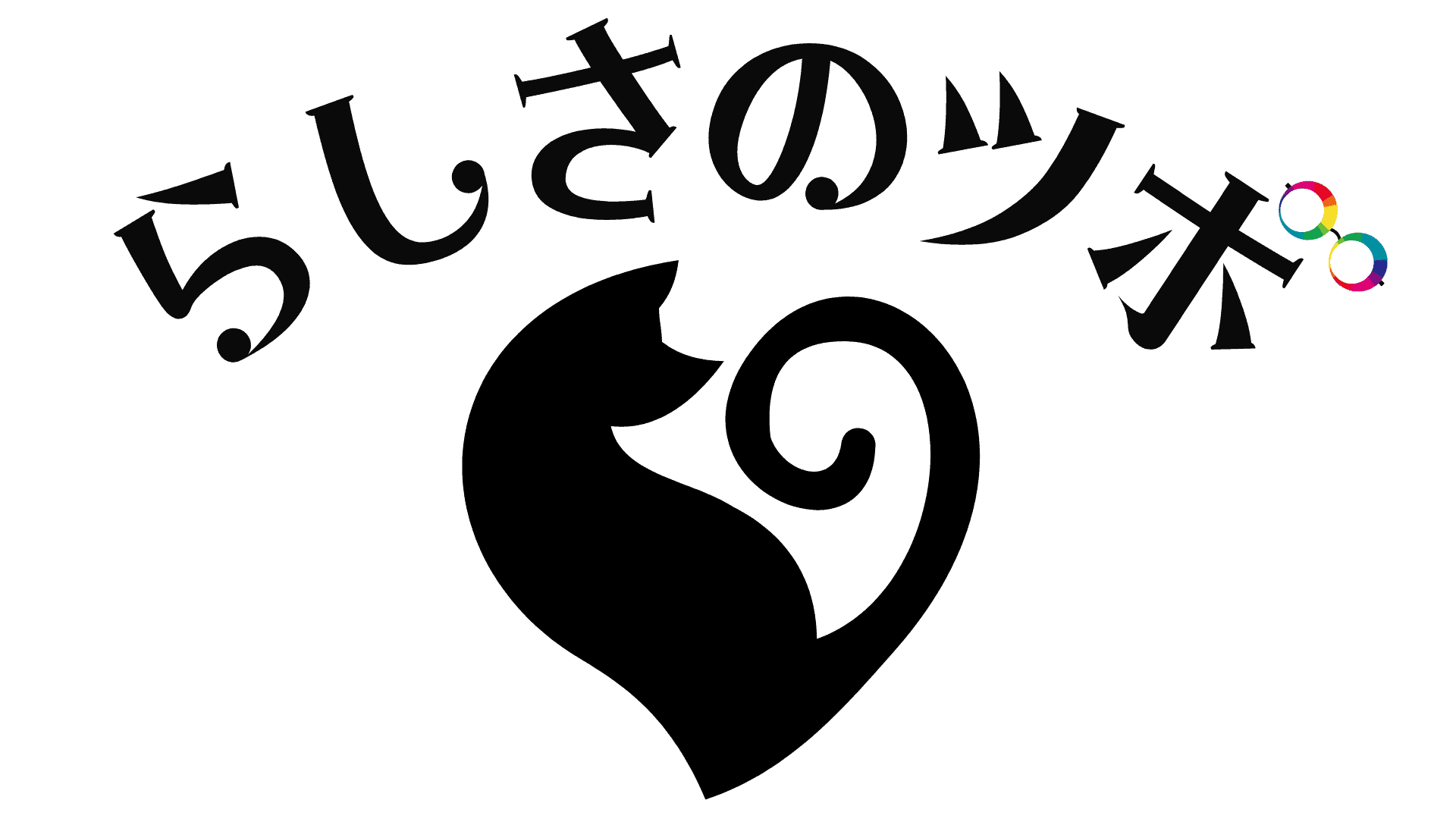忘れられない人になるのは、恋愛の話ではありません。ビジネスの話です。
選ばれるためには、思い出してもらうことが必要不可欠。
そして今や、記憶に残るためには、戦略が必要な時代。その戦略として「色」を使います。
そう聞くと「ふーん、お洒落の話かな?」と思われるかもしれませんが、少し違います。これは、“色を使った記憶操作”の話なのです。
なぜ“想起される人”であることが重要なのか?
情報過多時代に埋もれないようにするために
私たちは日々、膨大な情報に触れていますが、そのすべてを記憶できるわけではありません。
お客様も同じです。重要だと感じたこと、印象に残ったことだけを選んで記憶しています。
 かみい
かみい人の記憶は、毎日の情報がすべて詰まっているわけではありません。何かひとつ、引っかかったことや印象に残ったことだけが編集されて記憶に残るのです。
現代のビジネスでは、どれだけ優れたサービスを提供していても、「思い出してもらえない人」には、依頼も紹介も届きません。
これは実力の問題ではなく、「記憶と想起」の問題です。
人は誰しも日々大量の情報に接し、その中で“意味がある”と感じたことだけを記憶し、それを必要な時に取り出して「想起」します。
つまり、「選ばれる人」になるためには、「記憶される人」「意味づけられる人」になる必要があるのです。
その鍵を握るのが、“色”という視覚情報です。



つまり、私たちは誰かに「思い出してもらう(想起)」ために、記憶してもらう必要があります。
「私なんて目立たなくていい」と思っていませんか?
しかし、お客様に「あのサービスなら〇〇さん!」と思い出してもらえなければ、ビジネスチャンスを逃してしまいます。
特に個人事業主として活動する50代女性にとって、お客様の記憶に残ることは生き残りの鍵なのです。



では、どうすればその記憶リストに名前が載るのでしょうか?
「どこにでもいる普通の人」から抜け出すために
「私なんて取り立てて特別じゃない」「目立つのは恥ずかしい」というマインドセットは、日本人女性、特に50代以上の世代に根強くあります。
しかし、もしお客様に想起されなければ、「誰でもいいや」と一括りにされてしまいます。
AIがますます身近になる今後、「特徴のない」サービスはAIに代替される可能性が高まっています。



「誰でもいいです」は、「誰でもいいからAIでいいじゃない」に進化していきます。そうこうしているうちに、未来ではAIに仕事を奪われてしまいます。
長年培ってきたあなたの経験や価値観を活かすためにも、お客様の記憶に残る「あなたらしさ」が必要なのです。



想起(思い出してもらう)ためには、「あの人、なんか印象に残るよね」と記憶されること。それだけで、勝てる世界があるのです。
記憶に残る人になるには?──色と想起の心理効果
色は「非言語のプロフィール」です
色は、言語よりも早く脳に届き、感情や記憶と密接に結びついています。
たとえば、「あの人はいつも青っぽい服を着ていて、冷静で知的な印象がある」といった印象が、色によって強化されていくのです。
このように、色は「自分を記憶させる手段」として非常に有効です。
だからこそ、個人ブランディングやビジネスシーンでも、「どんな色で覚えられるか?」は、戦略的に考える価値があるのです。
服選びは、キャラクターの告白です
色彩には、人の記憶を強化し、想起を促す不思議な力があります。
それは色が視覚を通して直感的に認識され、感情や印象と強く結びつくからです。
たとえば、セミナーやお客様との打ち合わせでの服装。



大学の初講義の日、私が何を着るかは、毎年少しだけ悩むテーマです。天気や気分、そして「カラーコーディネートの先生らしさ」。
「らしさ」は大切です。もちろん、「らしさ」のある装いも大切。
とはいえ、若い世代のようなトレンドを追いかける必要はありません。
むしろ、50代女性としての品格と、あなただけの「色の個性」を融合させることで、自然な形で記憶に残ります。
また「自分軸のあるコーディネート」も、「らしさ」をパワフルに伝えます。



センスの良し悪しは主観的なもの。でも「なぜそれを選んだのか」という理由には、その人の人生がにじんでいるのです。
これは「目立ちたい」というアピールではなく、あなたらしさを静かに主張する方法なのです。
「キャラ色」は、色ではなく物語です
キャラ色と聞くと、派手な色や若々しい印象を思い浮かべるかもしれません。
しかし実際には、色そのものではなく、色を通じてあなた自身の価値観や強みをどう表現するかという思考法です。
単なる「赤」「青」といった色選びではなく、なぜその色があなたに似合うのか、その色があなたのビジネスにどう関連するのかというストーリーが重要です。



赤、青、黄色……それは入口にすぎません。キャラ色戦略とは、色そのものではなく、“色をどう使って、自分をどう見せるか”という考え方です。
50代という年齢は、若さではなく「深み」や「洗練」を表現できる強みがあるのです。



これは単なるコーディネートの話ではなく、ブランディングの話であり、思考術の話です。
主体的な選択が信頼につながる理由
トレンドより“自分軸”が信頼を生む
ある日のこと。大学での新学期を迎える朝、私はふと「何を着ていこうか」と考えていました。
カラーコーディネートの専門家としての印象を保ち、且つ季節感も考慮して…となると、気づけば去年と似たような装いになることも、多々あります。
けれども、私は、余りそのことを気にしていません。学生が入れ替わっているという理由もありますが、「自分の選び方に軸がある」と思っているからです。
たとえば、
Aさん:「流行を取り入れて毎回コーデしています」
Bさん:「同じ服を長年着ています。愛着があるので」
この2人が同じように素敵だった場合、多くの人がBさんに信頼を寄せるはずです。
なぜなら、選択に“理由”があるから。



「なぜ、それを選んだのか」という主体性こそが、人の信頼を得るのだと、考えています。
ブランディングは「想起の編集作業」です
「●●といえばあなた」をつくるには?
最近、日清カップヌードルが“野菜栽培キット”を出したという話を耳にしました。 ラーメンと園芸、一見何の関係もないように見えます
けれど、狙いは明確でした。 「食事とは無関係な日常で、想起される機会を増やす」という戦略です。



現代ブランディングの潮流です。想起されるためには、意外な日常にも想起の糸を張っておく必要があるのです。
「誰でもOK」「内容は同じだから安い方で」──この状態では、AIや低価格の代替品に簡単に取って代わられます。
だからこそ、「●●といえば、あなただよね」と想起される状態を築く必要があります。
キャラ色は、選ばれるための“非言語戦略”
「赤が似合う」ではなく「赤で覚えられる」
私が提案している「キャラ色」は、単なる似合う色診断ではありません。 それは、「自分という存在をどう記憶させるか?」というフレームワークです。
赤、青、黄色といった色それ自体ではなく、「自分がどんな理由で、その色を使っているか」にこそ意味があります。
選ばれる人になるには、まず思い出してもらえること。
思い出してもらうには、記憶に残る“何か”が必要です。 そして、その記憶を強化するのが「色」です。



名刺も服も「記憶に残す」ための小道具です。
ビジネスアイテムに一貫性を持たせる
たとえば名刺の色、服の差し色など。なんとなくではなく、戦略的な色使いが大切です。
それが「○○さんと言えばこの色だよね」という記憶につながっていきます。
その積み重ねが、あなたという物語を相手の中に築いていくのです。



統一感があることで、お客様の記憶に自然と残るようになりますよ!
服装やアクセサリーに取り入れる
毎回同じ服である必要はありませんが、ミーティングやセミナーでは、あなたの「キャラ色」を取り入れた服装やアクセサリーを身につけましょう。
スカーフ一枚、ブローチ一つでも、一貫性があれば印象に残ります。



色は、ただの飾りではありません。色は、あなたを伝えるPRスタッフの一人です。
オフィスや作業場にも取り入れる
お客様が来訪する場所があれば、そこにもさりげなくあなたの「キャラ色」を配置しましょう。
花瓶や小物、クッションなど、小さな要素でも積み重なれば大きな印象となります。



これは、キャラ色大作戦のエクササイズです。
まとめ:あなたは何色で記憶されたいですか?
「想起される人」になるには、他人の記憶の中で“意味のある存在”でなければなりません。
それは、選ばれるための前提条件であり、信頼される人の共通点でもあります。
色はその“意味”をつくるための、もっとも簡単で効果的なツールです。
あなた自身をどんな印象で記憶してもらいたいのか、
どんな言葉ではなく、どんな色で想起されたいのか。
ぜひ今日から、「自分の色を選ぶ」ことを、意識してみてください。



忘れられない存在になるには、思い出される存在になることが必要です。そのために「色で語る」という技術を、持っておいて損はありません。あなたが何者かを、一瞬で伝えてくれる武器。それが、色なのです。